餘部駅
(山陰本線・あまるべ) 2008年10月
夜の餘部駅
森の峰の中にある小さい待合室に座って足を癒しつつ、中年夫婦らの観光客を見送り、列車をゆかせるままにした。一時間も休むと辺りは急に暗くなり、今までの明るさは日没後の薄明だったのだと今さら知った。こうも暗くなると好都合だ。どう歩いても風景は見えないし、こうして終電を待っている時間が無駄に思えない。待合室は電灯の明るさを強め、しだいに蛾が舞い込むようになってきた。外はしずしずと降温し、冷たい風が音もなく流れ長袖でじっと立っていにくくなるくらいだ。展望される日本海は、じんわりと暮れなずんで、水平線上にただ暗い茜色の帯を引いた。
この暗紅色となった鉄橋の架け変えのため、木道のような構内踏切に防護要員が延々と立ち尽くしていたのだが、暗い18時になったとたん、持ち場を離れ、撤収に入った。確かにずっといるなら、気まずいなと思っていた。しかし仕事なんだから、時間がくれば、私なんかに構わずさっさと帰ってしまうのだ。何もかもこんなふうにあっさり動いていけばよいのにと思われた。
プラットホームは一線に街灯を煌々とともし、鉄橋の渡り口にある危うい踏切から望める暗黒には、漁火を眩しく焚くイカ釣り漁船が幾艘も浮かび上がっていた。わあ漁火、と歓びたいところだが、鉄橋や鉄道がどうなろうと、この集落は粛々と日々を送るだけなのを目の当たりにして、私は少し慌て、そしてその投光がやたら疲労を誘った。

 待合室前にて、香住方。
待合室前にて、香住方。
「しかしほんと水を汲んどいてよかった。」 駅から下りるには山道しかないのだが、それをちょっと窺うと街灯がほとんどなく、この寒さの中おりていくのは異様に心細く思えるものだったのだった。とてもでないが無理。下りられても、また上って来なくてはならないとなると。「町の人は、下りて我が家に帰りつくんだもんな。」 我が家に帰りつくのなら、こんな夜道など何でもなさそうだった。ちなみに昼に見た、西という集落へ下りる道を見ると、こっちはなんと街灯が点いていない。これは既知の道でないと下りられないだろう。真っ暗の山の中だ。
名月が鉄橋を渡った先の尾根から明々と顔を出した。気持ち悪いほど大きく、赤っぽかった。海からは、芯から寂しくなるような氷のように清明な風が渡り、私は、鉄橋の町の、人々によく知られているところという昼間の姿に、なついていたのに、今は、目を合わせても言葉を失うほど別人のようで冷酷で、町は外来者が立ち入居ることを拒絶する雰囲気を醸しはじめた。



 漁火が灯る日本海。
漁火が灯る日本海。
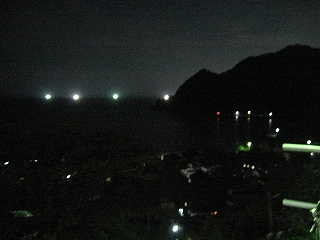
 鉄橋方。
鉄橋方。


 浜坂・鳥取方。
浜坂・鳥取方。
もうずっと駅にいよ、と思って、待合室に戻る。とかく虫が多い。蛾以外に不詳な奇妙な虫が空間に一杯溶け込んでいて、入るのさえ少しためらわれた。
列車が入ってきて、下車客があった。日中とは打って変わって地元の人ばかりだ。そのうちの一人、50後半くらいの作業着の人がゴミを捨てに待合室に入って来たとき、不思議そうな目をして、見つめられた。そして「列車逃したの」と尋ねられ、そういうことにしておいた。「もうちょっと早く来たら乗れたのに。今何時。あと、一時間もあるよ。あーあ。」そういって にやつきながらも いらだたしいそうな刺を含めて去っていった。やはり時間を無駄にした人を見ると、一日の疲れもあってか、納得いかない気持ちになりそうだった。しかしこの方の場合、間抜けだなあ、かわいそうに、というような情感があった。もしか、駅がこんな立地でなくんば汽車が来るまで休むようにあくまで形だけでも声をかけたかもしれない。
こんな集落ではどんな漁以外にどんな仕事があるのかなと思っていた。どうも近隣の街で現場作業に携わっているらしかった。
到着する列車や降りる人たちの気にかからないようにするのはたいへん、なにせ駅が小さいし、待合室も小さい。ほんと終電で降りるという鉄則を守ればわけもないのだが、予定上そう仕組むのはなかなか難しかった。それにここの最終は21時9分と、非常に早く、このくらいの時間なら夕方からでも待てると思った。
私は掲示物なんかを読んでいたが、帰って来る人たちは疲れていて、ゴミ箱にものを投げ込むようにする人もいた。よく見るとゴミ箱の側面がひしゃげている。誰かが思いっきり蹴り込んだらしい。そういや架橋もなかなかいい仕事だよな。反対なんてなさそうだ。
しかし何か飲み物を買っておけばよかった。退屈だし、乾燥してのども渇いた。だが今さら山を下りるわけにはいかない。特異なところにある駅だなと改めて思う。
汽車は一時間に1本だから、去ればもう駅はしーんとして、虫の叫びしか聞こえない。
木に蔦が絡んだような、もりもりした緑は暗黒を背景に白いライトで浮かび上がっている。
ずっと遠くの闇に信号が赤一灯で、しかし遥か離れたCTCに勤める人を想うのは難しく、夜の山だった。
じっとしていれば待合室の虫も何もしないと思っていたが、動かないでいればいるほど、体にまとわりつき、留まるようになり、何度も払いのけた。留まったままにしておくと、何だか死人になったような気になってしまうのだ。特に透明でふわふわ埃のように浮いている謎の虫には気持ち悪さのあまり悩み苦しまされた。蛾は蛍光管に何度もぶち当たった挙句、こちらを攻撃してくる。もうこのままではたまらんと、ついに竹ぼうきで何匹か蛾を叩き潰した。
蛍光管に無数に漂う虫を見上げて、待合室なのに人が待てないとはどういうことなんだろう、ここに吸い寄せられれば翌朝にはほとんど死ぬのにどうして集まってくるのか、そんな疑問が絶えなかった。灯りがなかったらこの虫どもは何をしているんだろう。
列車が一本行った。次で最後だ。掲示物ももう十分読んだし、退屈で仕方ない。何度か外に出ては、戻ってを繰り返す。外は10度ちょっとしかないが、待合室の中はプラス3度は固い。それくらい室内は暖かかった。「これなら寝られそうだ。」。
ふと、待合室の裏の雑木林で、パチッ、パチパチッ、と、柴の折れる音し、草むらを掻き分ける音がしはじめた。
「こんな夜更けに山道を歩く人がいるのか。気持ち悪いな。でも田舎ならありそうだ。」
とにかく早く行ってくれよ、と願う。
ところが、その人はしだいに、こっち側に近づいてきた。音がだんだん近くなってきたのだ。
「きこりか。こんな夜更けにか。」
しかしそのとき、フガッ、鼻を鳴らす音が聞こえ、
急いで待合室のドアを閉めた。しかし締め切ると不安だし空気も悪いし、少しは開けておく。イノシシはホームのすぐそこまで下りてきた。必死に日中のホームを思い出し、「たしか偶然工事で山側には丈夫なフェンスが立てられてたよな。あれ工事前はなかったんだよ。助かったもんだ。なかったら侵入してきてたぞ。」
イノシシはいつしか去った。ほっとしてドアを開ける。
終電まであと40分ほどというころ、駅への山道の暗黒から足音が聞こえはじめた。かなり早い速度で歩いている。こんな列車のない時間に駅に来る人はいないはずだ。とても怒っているような足音で、何が起こるのかと恐怖に包まれる。音はコンクリートの板をかかと歩きするような感じで近づいてくる。ドン、ドン、ドン、足音は近づき、極端に生々しくなり、緊張が頂点に達したそのとき、ある人物がこちらを覗きながら、そのまま通過していった。真っ黒の服装で、まぶしいライトを持っていた。「なんなんだあの人、て、それは向こうの台詞か。しかしホームの端に道が付いているのか? それだったら納得できるが。」
しばらくすると、再び足音が近づいて、そのまま待合室を過ぎ、帰っていったらしかった。どうもこの夜更けにここまで歩くのを日課にし、個人的なパトロールも兼ねているらしかった。
夜の駅といってもほんとにいろいろあるものだな。終電で来たらさぞかし楽だっただろうに、と思うが、こんな駅よく知らず降りたらにっちもさっちもいかなさそうだ。
待ち望んだ最終、21時9分の浜坂行きがやっと、到着。4時間は長い、もう待ちくたびれた。ともかく乗務員に見えないように配慮した。いったい何回目だ。見えたら、乗らないのかと気になるだろうから。こうして無事、餘部駅は営業を終了。
 最終列車を見送った。
最終列車を見送った。
最後に外に出て、辺りを見回す。汲んだ水で手を洗う。待合室に併設された狭苦しいトイレを初めて見つけたが、目立たなかったのも通りで、今は閉鎖されているようだ。屋外につけられた蛇口からも水は出ない。偶然元栓を見つけ蓋を開けて弄ってみたがやはりまったく駄目なようだ。ペットボトルからの久々に手にする水が気持ち良かった。麓で汲んだものだが、ここは海山が近いこともあってか井戸水のように感じられた。むろん実際はちゃんと上水道だろう。
幸い椅子の座面の虫の死骸は少ない。これは大きなポイントだ。ともかく払い落して、シートを敷き、夏用のシュラフを伸ばす。どんな格好で入ろうかとちょっと考えたけど、とりあえずは長袖、長ズボンのままで。充分であれば後で脱げばいい。さすがにジャンパーは脱いだ。
寝袋を使っての駅寝はこれが初めて。背中の痛さや枕のないことに驚きつつも、シュラフが化繊のためすぐに温(ぬく)とまって来た。しかも足元から。歩きすぎて火照っているというのもありそうだが。このシュラフは夏用で、大型スポーツ用品店で1000円で買った。今は10月初めごろだから少し無理があるはずが、この13,4度くらいの室温では使えそうだ。室内には風も入ってこない。

 地震などを考慮してこうして少し開けておく。
地震などを考慮してこうして少し開けておく。
 まあほんとに必要以外のものはない。
まあほんとに必要以外のものはない。
さっきの黒づくめの競歩選手みたいなのが入ってきたらどうしようかとも思うが、夜が深くなるにつれてここで降りる客は減っていったし、終列車からはついに誰一人として降りなかった。以降はなんと言おうか、人の来る気配がまったくない。ただ野性動物がちょっと心配だ。
蛾は、蛍光管のガラスの音と鱗粉を力いっぱい散りばめている。落ち着きがなくあっちこっち留まるから、寝袋の上に留まるのではないかと悩ましい気持ちだ。虫を見るのがいやなので顔までシュラフを引きよせているが、寝袋の表面にポトッと虫の留まるような音が聞こえると、必死に内側から叩いて追い払う。おまけにいつの間にか蚊が耳元に纏わりつき、死ぬほどしつこい。どんなに努力しても蚊があの音を立てて耳元に寄ってくる。そんなだから、とりあえず憂鬱に目を閉じて体を横にしているだけだった。
「今回は2日間の予定。今日寝られなくてもどうにかなる。」
突然列車がやって来て驚いた。気動車のものすごいやかましいエンジンが無人駅に響き渡る。案の定通過列車だった。しかし車掌室の人に見られたかもなどと思う。というのもこれ回送などではなく、18時6分大阪発、鳥取行きの「はまかぜ」。鳥取に着くのは22時32分だ。
少しうすら寒くなってきたが、それに応じて体は熱を帯び、その熱が化繊の寝袋に籠った。しかし熱を発したぶん疲れを感じる。きのうの夜明け前から列車に乗り、丹波霧に憂悶させられ、そして決然と晴れるという天気に気分を翻弄され、その後いくつも下車してかなり歩いたともあって、1日目だが意外と疲れているらしく、眠られはしなかったが、ふと気になって時計を見ると、深夜0時と時間の経つのが早かった。それにしても喉が渇いて仕方ない。朝は面倒でも麓まで下りて飲み物を買おうと決意。
それを最後に眠りに落ち、ちょっと目が覚めて夜の2時、板張りだから背中が痛い、しかしすぐに眠りこけて、いきなり目覚ましに叩き起された。
がばっと起きる。やった、ちゃんと眠れた、駅寝成功だ、と大喜び。時間というものをほとんど知ることなく、朝という場所に来られた。都合のいい時間にやって来れるというのは素晴らしいことだ。時刻は5時半。始発の1時間前になる。
待合室の虫どもはすっかりどこかへ去っていた。ホームへ出て夜明け前の清澄な空気を吸う。かなり冷え込んでいると思いきや、海辺のせいか それほどでもない。後で調べると13度くらいらしい。沖の方がかすかに明るいだけで、まだほとんど闇夜だが、もう恐れることはなかった。水も足りないし、のど渇いて仕方ないし、寝袋を纏めて下まで降りることにする。
山道を下りるが、街灯は最近増やされた感じがし、どうにかなった。昔もっと暗かったのだろう。
 朝5時半。
朝5時半。

 実際の暗さ。
実際の暗さ。
 明るめに撮ったもの。
明るめに撮ったもの。
 一人で山道を下りる。といっても、この辺の道は遊歩道に近い。
一人で山道を下りる。といっても、この辺の道は遊歩道に近い。


 明星の餘部鉄橋。
明星の餘部鉄橋。
 この灯りがなかったら何も分からない。
この灯りがなかったら何も分からない。
 寝静まっている集落。
寝静まっている集落。
誰もいない暁の餘部鉄橋を一人で歩いて視界を以って抱き、集落の小径を淡々と歩く。途中、ある家の玄関前に昨日声をかけてきた人と同じ服の掛かっているのを目のあたりにした。まさこここの人だったのだろうか。今はまだ眠られているだろう。
 レストランの自販機前にて。
レストランの自販機前にて。
 仮設トイレではなく本式の方に行こう。
仮設トイレではなく本式の方に行こう。

 常設トイレは、幸い灯りが点いていた。
常設トイレは、幸い灯りが点いていた。
鉄橋の下を流れて海に注ぐ川は、鉄橋の架かる谷に比してとても小さい。にもかかわらず、きっちり護岸してあり、やはり暴れるとみえた。これだけの深い谷はどうやってできたのだろうと思う。きれいなトイレに入り、手洗いをいする。鏡もついていて助かる。昼は観光客のほか、架け替え工事の人も使っていて、ここぞとばかり役目を果たしていた。
その後、ためらいなく飲み物を買い、駅へ登る。販売機の近くは国道がカーブしていて、渡るのが面倒だった。薄明でもあって、事故も起こりやすそうだ。朝まだきだが数台車が飛ばしていた。
気になる天気だが、日本海上には薄雲が押し寄せてきていて怪しい。高気圧の狭間だから不安だ。
 月もだいぶ西の方に傾いた。
月もだいぶ西の方に傾いた。


 鉄橋とともに生きる町。
鉄橋とともに生きる町。

 駅へ戻る途中にて。
駅へ戻る途中にて。



 鳥取発大阪行きのはまかぜ。こんな早い時刻に出ている。
鳥取発大阪行きのはまかぜ。こんな早い時刻に出ている。
駅についた後、6時台の上り始発をやり過ごすべく待合室に入る。飲み物がおいしい。
朝の忙しい時間に降り立つのを避けるべく、この列車は流すことにしていた。
そのうちの一人の爺さんがやって来て、煙草を吸い、室内で唾を吐いた。そのそばにある昨日殺した蛾の死体の翅が、風で揺れていた。
7時台の列車に乗るにはまだ少し早いなというころ、山道からなんとなく人の声らしきものが聞こえてくる。始発に乗る人だ。ようやく姿が見えると、おばさん二人だった。こうしてしゃべりながら山道を登って駅に来るというのは和やかな一景だった。
しかしその後 客らはどんどんやって来る。とくに女学生が多い。次々にホームに登りつく。そして昨日私に声をかけたあの人も同じ服でやってきた。しかし幸い客が多すぎて私には気付かないようだ。というか朝で苛々している感じでもあった。ともかくこんな狭いホームの崖の上の駅に地元の人ばかり、数えてみると、計30数人もが、上り列車を待ちわびるのだから驚きだ。たとい朝といえども、利用者はもっと少ないと思っていた。つまりは、ここは鉄道がたいへん便利なのだろう。なんといってもこんな大盤振る舞いな直線にしたのだから。まさにこの始発列車のために、この駅は存在していると、駅自身が言わんとしているかのようだ。
プラットホームの線ぎりぎりに人を携えてた駅に、満を持して煙吹く赤紫の豊岡行き気動車がゆっくり入る。剛性の車体が目の前に来た。エンジンのがなり声に、心の中で耳を塞いだ。
次のページ : 香住駅