花咲駅
2010年9月 (根室本線・はなさき)

































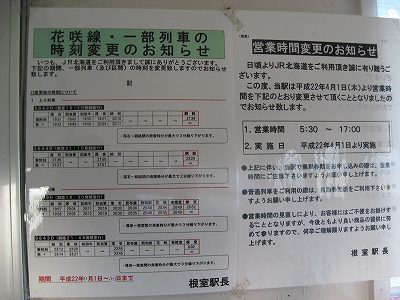

























肌寒さゆえの軽い頭痛、その頭を目覚ましに音で叩かれる。血圧が低い感じだ。もう外はまばゆい旭光が溢れている。ふだんは暗いうちに起きざるを得ないから、こうしていきなり気分を持ち上げられるようなことはめったにない。
昨晩三時間半近く乗ってここまできて、だいぶ疲れがたまっていたようだ。そう、駅寝旅は日にちが経つほどよく眠れるようになる。
「久しぶりに熟睡した」
あたりは草原で、また根室半島南岸の平らに切り取られた台地や、軟らかく滑らかな緑の崖が花咲湾を縁取っているのが遠くに見える。一面に朝の日の光が渡り、これこそ東の果てであった。
北海道の夏季は朝がとてもしんどい。朝が元気過ぎるのだ。しかもオホーツク海に突きさす半島の東端だった。
「こういう光景になるのね。」
こんな朝は私も知らない。道東は根室の人だけが知っている朝である。
駅の柵は鉄管を横にわたし、米印状に組んである。そんな柵にも北海道の粗野な感じや雪の結晶を想わないではない。北海道は風景がいいだけでなく、様々な事情から人が移り住んだことに悲哀があり、そこが雄渾な風景と厳しい気候と相まって、最も惹きつけられる点のように思う。
儀式的に車道まで繰り出す。車なんか走ってやしない。そして店も自販機もない。
辺りを見回して、なんでこんなところに駅がと思うが、牧場や花咲港の絡みがあったという。今は人々が活動した一縷の形跡さえ見出せぬ。それはちょうど中央アジアにて興亡した国家が跡形もなく消え去ってしまうに似ているかもしれなかった。もっとも、ここはそれほど昔のことではないので様々な資料から浮かび上がらせることできよう、けれど、こういう盛衰によって何もなくなってしまうのが、きわめて北海道らしいように捉えられた。それでよいのだ、と。人々の思いもつぶさな記録も何もかもなくなってしまって、消えてしまったものに消えてしまいうる自己が一体化する。そういう思想の大地かもしれなようなのだった。
旭光にあってなおも水色を保つ遠く水平の花咲湾を、苔のようなビロードの断崖が縁取る、その台地にいるのを実感すると、不安な心の動静は已むことがない。もう突端までまもなくなんだ。それ以上先はなにもないという都市に出遭うことになるんだ。花咲湾の水色は異様に哀しい水色だった。こんな東の細い果てにまで来て、なぜそんな哀しい水色で私を迎えるのであろうか。赤く明るい花咲は、南国のハイビスカスではなく、極東親潮の寒流に棲む赤く茹でらるる蟹だったのだろうか。
胸の騒ぐ異様な不安から救い出すように、始発の行き先は西向きだった。