口羽駅
(三江線・くちば) 2011年7月

宇都井から伊賀和志を経て、口羽へ。途中、江の川を渡った。夏日に彩られてそこは、もう抜け出すのに何時間もかかるような中国山地の真っただ中だった。もう三次のことも、山陽の諸都市のことも、思い返すことはなかった。そんなところからはもう遠い遠いところにいるのだ。そしてそんなところから始発に乗って旅をはじめ、そして今日一日は、この山の中の江の川沿いの駅をに降り立ち、またそうして一日を終えるつもりなんだ。
たっぷりと深い中国山地に抱かれつつも、鉄道という文明にあやかって旅するのは、この上ない贅沢で、しかしそうした失われた包容力を僕は、追憶の彼方まで追いづけているだけだった。
時間の制約が耽溺から私を救う。口羽、口羽です、と自動で案内される。ここではなんと19分しかない! というのも、交換駅で、ここで反対の江津方面の列車に乗るのである。本来、交換を終えた列車は速やかに発車するのだが、ここでしばらく江津行きの列車は時間調整するようだ。
一緒に爺さんが降りた。この人も趣味人だった。心の中で問う、爺さんどっち? ホーム? 駅前? あ、ホームね。じゃさき駅前行くから。さあ19分以内に戻らないといけない。





駅をかすめる新しい高架でだいぶ雰囲気はつぶれたなぁと思いつつも、ここは駅舎残ってるしまぁいいかとと急ぎ足で向かうと、気が付いたら駅前に出ていた。あれ? 駅舎は? ここはあったはずだか… ふと振り返ると、はじめっからホームから出て駅舎に向かうように設計されていなくて、完全に独立した待合室みたいな駅舎になっていた。でも石州瓦を葺いて、口羽駅と掲げている。
「これは珍しいタイプだな」
たぶんほとんどない。路線が完成するころには無人駅になるのがわかっていたのだろう。


駅舎の中はかなりきれいだった。正直ここで駅寝できていたら幸せだっただろう。でもそこを選んでいたら全駅来訪の予定は立たなかった。幅広のきれーな木製長椅子が置かれ、土間や腰壁の古風なモルタル仕上げも美しい。こういうクラシックなスタイルは、いつまでも新しいままだ。なぜか? その後の変化というのは、いわば装飾だからだ。壁紙はフェイク、大理石調の床タイルもフェイク、だから化粧材なのである。改札などは初めから設計されていないので駅らしさがないけど、玄関前はしっかりと口羽駅と掲出しているし、瓦屋根も駅らしさを語ってくれている。 にしても口羽というのは確かに記憶に残る地名ではあるなと。虫でも食ったようなというのはさておき、山間部からして朽葉、とかなのかなとも思うが、口羽の町を作った川は出羽(イズワ)川で、漢字はそろっている。




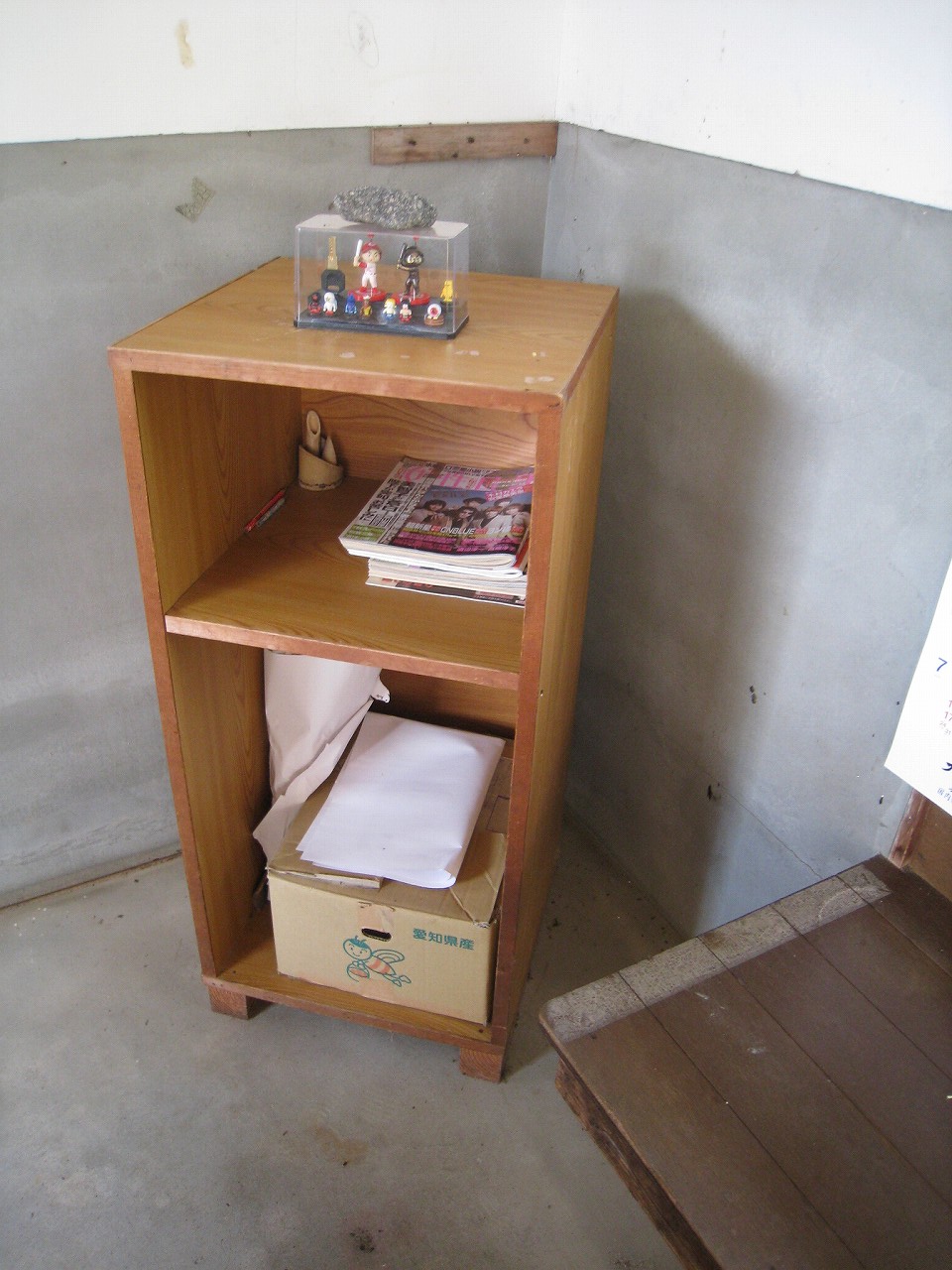







しかし駅から出ると新しい高架橋が頭をかすめ打ってくるので、なんか結構人口のある都市郊外みたいな雰囲気に身構えてしまう。
「いや、でもここ、中国山地のまっただなかだから。大丈夫だよ」と、駅前から早歩き。
高架まで上がると、車などまったく通らない、きれいでいい道が伸びゆく光景が広がっているだけだった。







なんかホームと道路が近い



高架橋はトンネルに吸い込まれている。主に口羽の集落をショートカットする短いトンネルだ。口羽は出羽川の屈曲したところにできた堆積地にできた町で、伝統的な町並みが残っている。訪れる価値はあるが、今回は割愛だ。にしてもこの県道7号、ほとんど車の通過がない。


江の川方


鉄道会の中では全通としては若い方です




ほんまシバいたろか思うようなバス停(すみません)





口羽駅駅舎その4.







ポスト公衆電話などインフラがそろっています

地元の名士なのでしょう




出羽川や三江線全通記念碑の動輪を見て、早々に駅に戻った。やはり町の方まで出ないといけなさそうだ。出羽川も堤防が高い支流という趣きだった。
爺さんはまだホームでぶらぶらしていた。もう乗っとかないと列車出ちまうぜ。





えらい遠いところまで行くんやな





ホームは白破線の残る懐かしいものだった。レール運搬車や倉庫、保線員詰所が見られ、交換駅の口羽は保線の拠点となっているようだ。場内信号機も久しぶりに見た。しかしこんなところではスタフやタブレットが似合うだろう。
もともと全通もそんなに昔のことではないので、信号が似合うと言えば似合うかもしれない。
レールや路盤と、脇道の境にはフェンスも何もなく、自由な感じだ。危険だとか、立ち入るなとかもない。そんなことは言わなくてもわかるだろ? といった、危険は自ら回避しなければ生きてはいけない時代の感覚がまだ残っていて、今も本来はそうあるべきだ、と。自らを死に晒すアフォーダンスを無意識に回避できない我々は、そのへんの側溝にハマって死ぬことも珍しくないだろう。いや、僕もだいぶ弱ってるんだ。慣れて気持ちが緩み、列車を警戒するのを忘れていることもある。かといって北海道の構内踏切では出発するために列車すぐ前の警報機が鳴っていても、客が渡って行ったりするのを運転士は認めているようなので、おおいに混乱する。まぁとりあえず、そういう遮断棒のない構内踏切は、たとえ地の人がどう動いていても、鳴ってたら入らないのを鉄の掟としていればよい。それでありえない事故は防げるだろう。この駅も遮断棒はない。やはり危機意識を試す一つの仕掛けとして働く要素を、この郷土はまだちゃんと抱えているというワケだ。









でも本来はこれでいいのである
自ら危険を察知しない者は、いつかは命を落とすのだから






急いで車内に舞い戻って腕時計をもう一度見ると、発車の二分前だった。確かに本数はメチャ少ないけど、気を利かせて声をかけてくれるということはないので、そこも注意。まぁこんなふうに腕時計とにらめっこじゃ都会生活と変わらない気もするが… 時計は1000円のデジタル時計である。これでよい。
ほどなくして折り戸を畳み、気動車は出発。さっきの爺さんも乗ってる。トンネルを経て、すぐ江の川をトラス鉄橋で渡る。夏の陽光は川面を照らし、些末な集落をあたため、そうして三江線は何度もふるさとの河を渡り、トンネルをくぐり、集落と町と村をむすんで、そしてそれは日本海までつづき、畢竟これほどの贅沢がほかにあるかといわれれば、たぶんないと、静かに車窓に向かって、私は肯じた。