国縫駅
2010年9月 (函館本線・くんぬい)







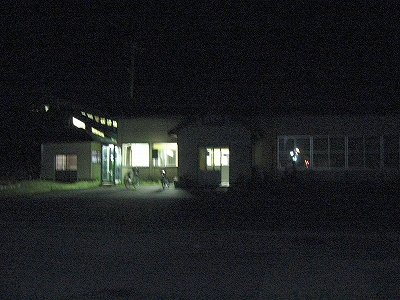




汽車に乗りながら各駅の情報を思い出す。たしか桂川は簡易な駅、だから寝られそうにない、など。むろんもっと先で寝る予定だけど。汽車は八雲を無事出る。この界隈では重要駅で、明かりもしっかり灯っている。
客は異様に少なかった。こんなていではお先真っ暗だろう。運転士は降車客の支払いのついでに必ず車内を一瞥するが、その度に彼は人々を怪しんでいるかのようだった。
一応目を付けていた国縫に着く。私は必死にガラスに張り付き様子を窺っていたが、国縫駅を見た瞬間、やはりここだ! とひらめいた。とにかく明るいところに色々の椅子がたくさん見え、駅舎も大きく、人がいっぱいいそうな時間もある感じがしたのだ。椅子は個掛けしか見えなかったが、賭けた。私は急いで前に向かい改札を受けて降りる。運転士はどこか朗らかそうだった。
しかし降りた瞬間、あれっ?と思う。まだ汽車は止まったままだが、なんか思った以上に寂しい空気が漂っている。まぁ…まず気温が違う。確かに北海道の空気で、いちおう来たんだなとは思った。さまざまことを考えながらも、跨線橋に差し掛かった瞬間、どきっとする。なにか違う…なんだろう! 跨線橋を上がりきると、異様な古めかしさだった。汽車は眼下を去っていった。
騙されたかもしれん、と思いつつ、とにかく駅舎のある乗り場へと急ぐ。全体とそしてガラス越しに中を見て、これは外したな、と思った。勘違いしたのだ。ただのやや大きめのやたら古ぼけた駅である。少なくとも戦前のものだ。中に入ったがやはり長椅子も飾りもなかった。
とにかく外に出よう、と出た瞬間、風が吹かれ、もの凄い勢いで寂しさに襲われた。ぞくっとし、体が固まって動かなくなる。死を忘れるほどの凄涼さだった。見えるのは、ただ漆黒の塊だった。そして外灯がかすかにすぐ近くの草々を照らし出しているに過ぎない。とにかく目の前があまりに黒すぎて前に進めず、私はただ灯りのある駅舎の玄関口に呆然と佇立するばかりだった。
「うそだろ…これ…」
世の中にこんなにも寂しい一景があるのを私は未だかつて知らなかった。舌打ちする気持ちで、
「騙されたな。騙したな。」
まるで何かにこの駅へ引き寄せられたかのように感じていた。
「どうすんだこれ! ってどうしようもないだろ! とにかくこの個人掛け椅子にシュラフを敷いて寝る。それから…」
もう何時間もまともに水分を取っておらず、からからで死にそうだった。寝台が遅れてからの乗り継ぎがそこそこスムーズなのはよかったが、それで食糧調達の時間が取れなかったんだ。
「とにかく国道まで出よう。道が怖いとか暗いとか言ってられない。このまま朝まで我慢したら」ほんとに死ぬぞ、と、けしかけて初めて、ようやく暗黒の道を切り開く決意ができたのだった。
肚に力を込めて漆黒の塊を坦々と突っ切りはじめる。そのうち変わるだろうと思ったが、まったく質量は変わらない。苦しく、まるで黒曜石のナイフが裏返しになったかのようだ。息を凝らし歩き続け、国道に出たところ、意外にもコンビニにともしびが、なんてことはなかった。四角い建物は結構あるのだけど、店の灯りは見当たらない。しかし自販機は一台だけ光っていた。迷わず横断し、500mlのコーラを購入。その場ですぐ開栓して思いのままに飲む。
ここは駅から国道までやや距離がある方だろう。怖さをさっさと終わらすために駅へとすぐ戻った。
駅舎内に入ってからまたすぐに飲む。
「飲み物も確保したしこれで何とかなったな。これで最大明日の昼くらいまではいける。」
人工甘味料ものやお茶ではこうはいかない。
駅の敷地内にいるから安心とは感じなかった。施設が押しなべて古いのだ。何十年も吸い続けた時代が夜になって発散されている。外は涼しいが、さすが北國造りで中は変に暑い。これが悪夢の引き金となる。椅子は一人掛けだし、快適な要素はさっき買った冷たい飲み物くらいだった。
何度か駅務室の方から音がし、誰かいるのか、と思う。何度も視線を感じては、ポスターに大写しの若い女性と目が合う。そんなことが続き、私は「参ったな」とその度に連呼していた。
「何か妙だな。普通の駅じゃないみたいな。国縫ってしっかりした感じなのに。」
と、そのときだった。電気が突然消えたのは。思わずぞっとする。でもここは明るく、「あーあ消えちゃった、だから言ったのに、お前終電で来たんだろ? 忘れちゃ困る」と、空元気出して椅子にシートを敷きシュラフを広げさっそく横になる。
横になりながら、
「明日ですら道東に行けないんだろ? こんな調子でやってけるのか?」
シュラフが暑かった。ほとんど羽織るだけにしている。それでも体が熱を持ってしんどい。原因は寝台列車だ。十八時間も閉じ込められ、その疲れが蓄積していた。そういえば風呂にも入れていない。予定では入れるはずだった。早くも旅行失敗が脳裏によぎる。
しかしどうも誰かいる気配がする。実際に誰かがいるいうより、気配だけがある。
「あのポスターじゃないの。ったく、迷惑なことだ! だいたいいまどき女の大首絵とか田舎千万じゃないか! まったく古いんだよ何もかも…。」 そうしてポスターのせいにして片付けた。
そしてついに、金縛りに遭った。北海道の誰もいないとある地の一人駅寝で金縛り…それは恐ろしいことこの上なかった。必死に呼吸してやっとの思いで呪縛を解く。はぁはぁいいながら自由になった体でただ自分が暗い駅舎の中にいるのを感じる。「だいたい生きているものの方が偉いのに!」なんていう台詞を吐き、目をつむって横になったまま肘を横に張って肚を据える。「まさかこんな駅だとは思わなかった。とにかく気配がするが、朝まで我慢だ。」
魑魅魍魎は朝の快刀にまかせることとなった。