北陸・信越1
2009年9月


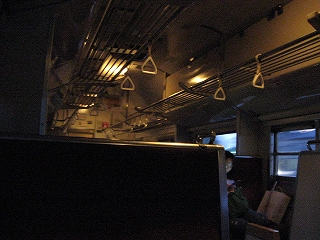
親不知の湯
最後の黒井駅で汗かいて列車に乗ると、すぐに大駅の乗換案内だ。その列車に乗り続けていた人はやっとかという心境で、万感の思いにみなぎっているところだが、私はと言えばそういうストーリーの最後の部分のところにだけ闖入した形で、ひと駅で乗り継ぎはしんどいとだけ思っていた。こういうところは列車旅のロマンの中でも、なかなか生活的なところ、旅の生活といったところらしい感じだ。
車窓からの太陽は廃れ、客室の皆はだれている。慌ただしさと混迷の中、夕刻の直江津で人々の乗り換えは行われる。旅情もなく、石造りでない新しい階段はどんどん踏み鳴らされる。さらに西にゆく列車まで走る。端の方の切り欠きでぼろが停まっている。間借りらしい感じだった。それでも車掌は背筋伸ばして振り返り、走ってくる客らがたどり着くのを見届けんとしている。
白っぽい車内にビーロド調の鮮やかな朱のモケットが映えているが、きれいなのはそれだけで、床や造りはだいぶ年数が経っているのを隠そうとされていない。旧寝台を片付けたボックス席から長椅子まですべて埋まり、吊革の立ち客もいた。食料品を下げた家庭の女の人が目に留まった。わざわざ直江津まで買い物しに来たのだろうかと思う。本を読んでいた。
発車前、今日もJR西日本をご利用くださいましてありがとうございます、からはじまる車掌による異様に丁重ないつもの放送が始まり、動く前に切符を売りに来たときも、ありがとうございますと何度もいいふれ回って、こんな古い客室の中でも、礼儀正しく、制服も硬く着こなしていて、きらりと光るものがあった。このへんは隣会社との差を客らに見せつけているとしか思えない。昨日ぶしつけな検札があっただけに。食料品の女人は能生まで求めた。
発車後、旧寝台改造のための狭い客室内では、立ち客の手提げ荷物が揺れ、そわそわ席を探すその背中に座り客への緩い不満を私は汲み取る。
ぜんたいに、旅行者はいなくないが少なく、ほとんどが地の人の利用と見える服装と会話で、それが折り戸のある古びた車内によく合っていた。人々は朱のクッションを張ったそそり立つボックス席の硬い背もたれに互いに背を任せ、見知らぬ人も同席しながらもその人のことは気にせず、会話が交わされていた。回ってくる車掌も、独自の接客の世界に入っていて、むやみに客と融和はしていない。
私も気分が楽になってきて、とつぜん鞄から昼に買ったランチパックのパンを取り出して、長椅子で食べはじめた。はちみつの入ったもので甘くておいしそうと思って買ったのだが、食べてみるとなぜかだんだん苦くなってくる。なんかおかしいんじゃないかと思え、半分食べて元に戻した。しかししばらくすると、半端なのが気になって、また、食べたくもなって、食べきった。
蜂蜜のとろとろした光が、西頸城のトワイライトゾーンを走り、日本海海岸の中空を泳ぎ行く、襤褸の旧寝台車に流れ込んでいる。はだけたカーテンが光で刻々と傷んで裂けやすくなるようで、心の中であわてる。そこからの車窓が苦いとは考えたこともなかったが、甘いは言うまでもなく、かいた汗による鹹水感で捉えるより意外性があり、自分の放浪的な駅の捉え方の裏側に存する、着実な捉え方、まったくの無意識のあるがままの様相、それが決して苦々しさという意味ではない、苦味という単なる一感覚によって、透明に表され、無味とさえ換言できるように思われた。はや苦さは苦さでなく、緑茶みたいなものや、ピンホールの像を正立と捉えるようなことかもしれない。言葉すらなく、光と、食物と、ただ生きていることそのもののように思われる。これまでは夥しい粉飾に溺れ耽っていたのだろうか。そうではなく、それは経験の一面で、やがて併せ持つものの片面を構成するものなのだろう。
この人こそは旅行者だろうと思っていた人も、駅に着くとなんのけなしに飛び降りて、そのまま帰路に着く、そんなシーンばかりで、よくてもスーツケースを牽いた里帰りだった。「旅行してる人なんてそんなにいないのかな」。
北陸本線東端の黄金区間の無人駅をそうして一つ一つ停車しているうちに意外にも蜜は濁り、腐り果て、梶屋敷に着いた頃には薄明も終わって暗くなり、ホームに男子高校生3人があぐらをかいてたむろしているのがようやく判別でき、その光景に驚いたくらいだった。そういえば今年も夏は九月に出かけたのだった。でも夏の九月は落ち着きがあっていいものだ。もとい、どうしても浮ついて落ち着かない八月は耐えられずやり過ごしたというのはありげだったけど。
糸魚川に着くころにはほとんど夜を迎え、寝台列車のことばかりを思い出す。そもそも日本海側のこんな主要な駅は、そのために深夜まで人が詰めることがあるくらいなのだから。しかし厭いは少しも想われず、遠くから汽車で古里に帰ってきた迎える駅だ。糸魚川は、新潟のような、富山のような、そして長野との繋がりもあり、独特な故郷感がありそうだった。
ここまで帰ってくると私は少し安心する。やはり西頸城のあの人里離れた絶海の印象は縦貫線抜けるといえども孤絶して寂しいのだった。糸魚川までくれば、もう親不知を越しさえすればよく、そうすればまだ泊あたりの寂しさはあるも、それは国営の夜のニュースのような始まりのしめやかさで、やがては明るい街を迎えるのであり、そうして富山平野の端緒には少なくともつくわけだ。親不知はというともう何度も降り、既に懇意にしているとまで感じていて、安心するほどなのだ。
それに今日はそこで一旦降りるつもりをしている。だからこれ以上長距離乗車がもたらす漠然とした不安さえもないわけで、つまり、何も心配いらないんだ。


















無事、わずか二駅先の親不知に着き、下車した。この駅では寝たこともあるし、ただやっぱり闇夜の潮騒と頼りない蛍光灯、踏切より前に鳴る、通過列車を知らせるポーッ、ポーッという音の寂しさだけは、覆いかぶさってきている山の斜面の影の暗さとも夜の暗さともつかない暗黒によって二倍に膨らんで、どうにも、やりきれなかった。駅から出ると鬱蒼と暗い山沿いのしじまと秋冷えに包まれる。明かりが少なく、目的地の載ってる観光案内板も読み取れない。この時間はもう読んではならないのかとすら思った。
今日はここでお風呂に入りつもりだ。そう、この暗黒の先には、明るい施設が自分を待ってくれているはずなんだ。












けれど歩きはじめると、想像していたよりもずっと暗く、そして異様な寂寥感に包まれる。おまけに、こんなに遠かったか? と怪訝な気持ちになった。もう何度も来たからだ。
曲がりくねった旧道は、絶え間なく波音を聞かせ、破線上に明かりを灯す海上橋を眺めさせる。トラックは悲痛な叫びを上げて走破するが、山裾は沈黙していることから、真っ黒な山が質量的に控えているのを認識させる。行方知らずの道が取り付つく、誰も興味を持たない山だ。さらさら落ちる、昇りはじめの月色の街灯は静かに円錐の光で、自分の歩く足音がひたひたと真に聞こえてくる。暖かく薄いシトラスな色とも、レモンと言い切れる、頂点から降り落ちてきた偽りの暖かさという寂しさは、路上の円光数センチ上で生き物のように泳いでいる。私はその光をまもとに浴びぬよう、その円錐に入らないよう、避けて通った。そこが明るいところだというのに!
「こんなところで連れ去られたら一巻の終わりだな」。
とりあえず、自分をしっかり持って歩く。目的は入湯だ。半袖の服に肩掛けのベルトが食い込む。何度もしょい直しているから、肩はすっかり赤剥けて、ときおり痛みで苦りきる。それも思い切って癒したい。
海上橋の遥か彼方には、かすかに暗い薄明を残す群青色を背景に、入道雲が不気味に盛り上がっている。確かに夏ではあった。
海上橋の下にわびしく覗かせる砕け散る白波、また下の国道の路面の斜線誘導帯が、例の寂しい偽りのランプに照らされているのを見るたびに、寝台特急日本海の夜の車窓から、そんなものがいくらでも見えたことを思い出す。などてかくまでさびしからん。今にも身を、具体的な方法ではなく、幻覚的、精神的に、にどこかへ運ばれてしまいそうな気がする、波に攫われてしまう気がする。北陸道日本海沿いに生きる人々は、どのようにして自己を保ち、岩から離れずに済んでいるのだろうか。
「こんなところ夜に興味本位で歩くもんでもないなあ」
「でも湯があるんだから、こうしてやって来る人もいるだろう。」
それより先は本当に真っ暗になり、これ以上歩きつづけたくない、と思っていると左脇に斜面を急登する山道が現れ、街灯が二つほど点っているのを見つける。湯へのショートカットだ。
「なるほど、これを使えということだな。だって街灯がついているし…。これ以上車道伝いに行ったら余計に長いことくらい道を歩くことにもなるしな。」
せっかく徒歩で距離をつづめられるのに、遠回りの車道を通るのはいやだった。山の中腹にあるから、勾配を稼ぐ車道は距離が延びるのだった。おまけに街灯はまったくない。
よいしょと山道にかかる。あちこち夏草が突き出していて、登るたびに虫が茂みの中をとんとんとんと移動する、草に重みが乗った音がする。寝袋を入れた鞄がほんとにじゃまで、何度も脇の草を均す。当たり前のように絶えずコオロギが鳴き喚き、歪んだ足場ゆえ何度もよろけ、立ち止まる。上を見上げるとまだ長い。おまけにほとんど灯りのない区間がある。ふと怖くなって、車道を使う決意をし、急いで元の道に降りた。「いくらなんでもあんな山道を夜に使うのはおかしいよ!」。しかしいざ元の道を歩き出すと、体力と何よりも時間が惜しくなり、「同じ苦痛なら短い方がいい」と、こんどはさっきの山道をがしがし登り詰めはじめた。先をあまり見ないようにして、足元を見ていれば大丈夫だった。振り返ると、海上橋よりも高くにいる。海から離れきらないのは安心でき、トラックの走破音さえ、よく見知った風景と縁が切れていないことを思わせてくれた。二、三分でコテージ風の建物が現れ、「これか、これだ」。なんとなし電気がついている。ここは親不知まるたん坊といい、少年自然の家の小さいもののような施設なんだ。




























硝子戸の向うは遠くに薄く明かりがついているだけで、やっているのか不安になるが、ドアを押すと同時に営業時刻が目に入り、その通りにドアは奥に押しやられた。湯は二階で、一階には何もない。靴脱いでスリッパはいて、狭い階段を上り、洋間造りのロビーに着いた。しいていえばリビングのような感じでしかない。かなり年輩の係員に挨拶して、すぐ金を払おうとするが、後ろに券売機のあるのに気付き、そこに入れる。係員は事務的だった。公営だろうか。のれんをくぐり脱衣所に入ると先客はいないようで、一人で湯に浸かった。
湯桶に湯の落ちる音は、仮にここから海の風景が見えていても、それを隠してしまいそうだ。明るいうちに来たら、それなりにロマンはあるだろう。浸かりながら、「それにしても、ついに親不知の湯にも入ったか。やりたいことが終わっていくなあ。」 一人なのをいいことに、立ち泳いで、洗っては、また浸かって…。上がろうと思っても、せっかくだからともう少しとまた入った。
体が温まってから、再度窓辺に乗り出し、ハンドルで押し開いて、意識的に一端の親不知たる風景を見つめる。夜の秋風が体を冷たく煽り、海上橋よりも高いゆえ、しきりに夜行トラックの走行音が、湯殿の温蒸気をからからと平然として破り続ける。それは奇妙なもので、親不知を音風景によってどこにでもある陳腐にするやいなや、この道の寂しさや特殊性を次々と救っていた。だって窓を開ければ高速道、なんて、お昼の都会のマンションにさえあるではないか。そしてそれは、朝、ここで坂を下るとき、海を見るまでは、この地区は音によって平均化された場所だと思えてきそうだった。そしてそのことが、この国にある海に臨む町―東の大都会であっても、山陽であっても―としての一体感を持ちえそうだった。
窓を閉めて、泡ぶくれる湯に身を沈める。それは風呂場の湯ではなく、親不知の湯で、しだいに体の中に親不知の実存感が内省的、目を潰された者のようにたぎってくる。
どれほど入湯したいと思っていたとしても、体はこれ以上の時間応えきれず、さっぱり諦めて上がる。荷物の整理は出てのところでした方がいいと思い、先の係員にしばらく休んでいいですかと訊いて、返事をもらってから、ロビーに座りテレビ見ながら片付ける。畳敷きの休憩室の方がよかったが、電気が消えていた。親不知と浮き出させた水色のバスタオルなどの親不知グッズが販売されていて、まさにこういうものがほしかったと思う品だ。しかし誰かが考えるものなんだな。極め付けにまだ浜が残っていたころと旧線時代の写真が飾られていて、思わず見入った。本当にこのころ来たかったと思う。旧線は見られなくてもいいから、親不知の古道を通り、大穴、小穴に身を隠してみたかった。
しばらくすると、ゆっくりした物腰で係りが話しかけてきて、
「なにで来たの。」
私は努めて明るく、
「鉄道です。親不知駅から歩いて。」
暗いのはいやだ。主体的な明るさがほしい。
「鉄道。鉄道ね。ふーん。」
唐突に、
「何時のに乗るの?」
直近では20時58分のがあった。しかし一本後、
「21時に一本あると思うのでそっちに乗ろうと思ってます」
というと、
「そんなにないって。やってないよ。」
という。
地元の人間で、宿泊施設に勤めてるのに汽車の時刻も知らないのかと思った。
「やってないよ、ここ」
ようやくすべてがわかった。この人はその時刻までこの施設に私が居座ると思い込んでいたようだ。しかし、ここが閉まる20時まで、まだ30分弱はあった。私は居座るように見える行動や"なり"をしていたんだろうか。仮にそう見えたとしても、もう閉めますと一言いえばいい話だ。この人はとかく、不安だったらしい。
「ここがですか? 後どれくらいで閉めるんです?」
「もう閉める。」
仕方ないので、玄関まで降りると、その人は付いてきて、うれしそうに
「山降りる道知ってる? あそこに明かりがついてるところあるでしょ、駅行くんだよね?」
私は明るく、
「ああ、来たとき使いました」
「使った? あっちの方が近いから、ね。」
と言って、私を送り出すと同時に、鍵を閉めた。
「まだ20時になってないのに…こんなんで早く閉められて入れなかったら悲惨だな。早く来ておいてよかった。」
一度通った道とはいえ、あの山道のところまで来ると気が重くなった。道は、海上橋と対面しながら、ときには左右につづら折れながら、下っている。「あの人あまり情に篤そうではなかったなあ。東というより、この厳しい地形ではそんなものなんだろうか。」 ごまかすようにして、よいしょっと声出して急坂を降りる。一人ぼっちの風が身にまとわりついてくる。でももうそれは私の友達だ。けれど降りている途中から怖さの方がまさって、最後の方は駆け足で下り、旧国道まで出るとスカッとした。そのまま何も考えずにさっさと暗い道を歩いた。ゆっくりしても無駄だ。もちろん20時58分のに乗ることにした。一本遅らせた方が富山で高山本線にそれほど待たず乗り継げるし、その一本までの間、ここでロマンチシズムを堪能しようと思っていたが、もう十分だった。退屈して買ってきたパンと駅を撮って遊びさえした。親しくなるとは、そういうことかもしれない。自分だけの濃密な夜というものとは、もう、別れるかもしれなかった。







楡原へ
親不知から夜汽車の中央の車輌に乗ると、次は市振ですと言い終わるや否やマイクを掛ける音がし、さっそく車掌が出てきたらしく、巡回の後ろ姿に出遭った。券売機があるのに、と思うと、どちらかというと車内保安のためかと思った。こんな夜更けにあそこからどんなやつが乗ってきたのか、閑散区間で客室で妙なことが起こっていないか…。とりあえず、車掌は巣に戻った。
真っ黒な鏡になった車窓で、自分の顔を見つめた。一人で何をしても寂しくない、心にかたくなに甲冑をまとって彷徨する一人の人間がいる。
泊まで来ると、初めての有人駅とその地形にほっとするが、まだ緊張は解けない。駅前は暖色街灯のもとタクシーがじっとりと駐まっているだけだ。ここだって断絶地点の手前なのだから。それ以後ちらほらと客を乗せて客室に人が増えてくると、ようやく人心地がついた。つまり、あまりに人が少なさ過ぎたのだ。夜の富山東部、親不知は、精神が健全でも、本当に心細い。道はあるのにこんな最果てを味わせんとする海沿いはそうそうないだろう。
一時間以上かけて富山へとたどると、それだけでただひと仕事という感じだった。まあ立山そばも何もかも閉まってるけど。時刻は22時をとうに過ぎている。ほぼすべての駅が営業をとうに終えているだけに、富山がしっかり改札をやっているのを目にすると、或る矜持とも厳格さとも捉えられた。構内は酔った人も少なくない。歩いていると、カップルの制服の高校生が仲睦まじく体を柔らかくしながら談笑していて、そこを私が通りかかると、男のほうがいきなり、ですよねぇ、と笑いながら声かけてきた。女のほうはそれを見て、あははは、と笑い上戸になっていた。私はそれに微笑み返した。一方は私は一人でこんなことをやっているのが楽しくて仕方なかった。この世一般の喜びと訣別して久しかった。
富山のホームで三十分ほど待っていた。こんな中途半端な時期に、自分と同年代の者はいない。いたとしても、何かもっと明確で世間で通る目的での人だろう。もしかするとそこに若くしての山屋の人もいたかもしれない。そこに私と相通ずるものはあるも、その共通項が出会いを不必要とし、この世に無関心である以上、互いにその存在に惹かれることもないだろうし、その存在に気づくことさえないだろう。それは若いころの一種の過ちであったかもしれないし、もしくは最終的に一人にならざるを得ない予知からくる、修練と道の確認であったかもしれない。この世における自分を捨て去っている以上、眼前に現れるものがすべてになって、自分の過去と将来はありえないのだった。夜の富山駅の風がそのままにプラットホームで自分の身を取り巻く。帰路でもないのに今から高山本線の短い区間を乗る異様さも、そのままに受け入れないといけない。
高山本線は二両の気動車が控えていた。最終だというのに混んで客が立ち、座っていたが私も詰めて、脚が両隣の人と接した。やはりベッドタウンになっているみたいだ。ツーメンだったので、一人がまだ動かないうちに車内放送を流す。これが高山本線の最終、猪谷行きで、ドアは自動では開かないから手で押せということだった。その放送中にも次々とステップを上がって客が乗ってくる。気動車のがなり立てる音と車内の窮屈さで、慌ただしいく苛立たしい雰囲気にすっかり支配される。座り客も俯いて押し黙っている。そうするしかないんだ。そんな中でも、立ち客の中には闊達に会話している人もいる。お酒を飲んだのだろうなと思う。
列車が出ると、到着駅を知らせる罅割れた女声の自動放送と先の添乗の男性の肉声が併用される。気動車は乱暴に右に傾き左に傾きして疾走し、横座りの客でさえもかかってくる力と振動で疲れさせた。非電化の身体的影響における貧しさが顕わになり、こんな列車に押し込められて帰る惨めさはあるにあった。交流電化の北陸本線が一流に思える。
キハ120系の大きく平たい窓から見る、駅に着いたときの光景はいつも独特だなと思う。構内と車内が近く、親和している。停車中でも車体は揺さぶられ、頭に蛍光管の付いた駅名標が揺れて見える。西富山や速星は、まだ平野だ。客らは富山に近いところほど、たくさん降りていく。集札はなかった。ドアの開錠に手を取られるからかな。構内に入る度に自動に追随して駅名がマイクで読み上げられ、手で開けるようにと言われる。開かないと騒がれることほど遅れることはない。